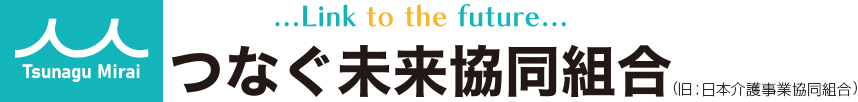技能実習Q&A
こちらでは、外国人技能実習生受入れに関して、よく寄せられるご質問にお答えしています。 以下で掲載している内容以外にも、ご不明な点がございましたら、お気軽につなぐ未来協同組合までお問い合わせください。
- Q 技能実習生にはどういう人が選ばれるのですか?
A 厳しい選考をクリアした優秀な若者です。
選考基準に合致した応募者の中から、日本介護事業組合員及び現地スタッフが面接し、人間性・熱意などを重要視した上で、能力テストの結果成績優秀な18歳以上35歳未満の若者が研修を受けることができます。
- Q 技能実習生の日本語は?
A 簡単な日本語を、読み書き話すことができます。
技能実習生は、選抜されてから研修開始までの期間に母国で日本語を勉強し、日本語能力試験N4程度の資格を取得してきます。 さらに日本入国後、2ヶ月間当組合において、日常会話・専門用語・日本の文化・マナーなどを学習していきます。 個人差はあると思いますが、受け入れ施設に行くまでには、ひらがなの読み書きができるように、また簡単な日常会話はできるように教育いたします。 (介護職員初任者研修資格が必要な場合、別途研修費が必要となります)
- Q フォロー体制は?
A 日本介護事業スタッフが受入企業及び技能実習生の指導・助言を行います。
受入企業に定期的に訪問を行う体制を整えています。1年目は月1回以上、各受け入れ施設を訪問して、さまざまな問題や疑問に応えます。
- Q 突発的な事態への対応は?
A 24時間連絡可能な体制です。
技能実習生の受け入れ後、突発的な事態に速やかに対応するための連絡体制を整備しています。
- Q 技能実習生と問題が生じた場合は?
A 外国語が堪能なスタッフが即対応します。
日本介護事業では、ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語・英語が堪能なスタッフを本部に配置しており、 母国語での対応が必要な際には直接出向きます。ただし、必要経費は受入企業のご負担となります。
- Q 技能実習生の傷害・疾病等の備えは?
A 技能実習生総合保険に加入していただきます。
技能実習生は、一般の労働者と同様に社会保険が適用されます。
実習期間中の疾病・傷害の場合には健康保険で受診し、診療代の3割を自己負担します。 そのため、「技能実習生総合保険」へ受入企業のご負担で加入していただくことにより、実習生の自己負担分をカバーすることを目的としています。
特定技能Q&A
- Q 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
A 転職は当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが前提です。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請を行っていただく必要があります。- Q 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
A 日本人の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- Q 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
A 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
- Q 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
A 11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。- Q 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
A 下記留意点があります。
報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
- Q 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
A 永住許可を受けるには要件があります。
要件のひとつとして、「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」と定められているところ、要件にあるとおり「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれないほか、「特定技能1号」の在留資格で日本に在留できる期間は最長5年であるため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
一方、「特定技能2号」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれるため、「永住者」の在留資格へ変更することが可能です。- Q 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
A 在留期間は1号特定技能外国人・2号特定技能外国人で異なります。
1号特定技能外国人については、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間が、2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。- Q 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。
A 可能です。
- Q受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。
A 社会保険に関する法令を遵守していることが基準になります。
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
- Q受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
A 下記支援が必要になります。
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。
- Q住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
A 保証人になること以外に下記支援が必要になります。
外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。